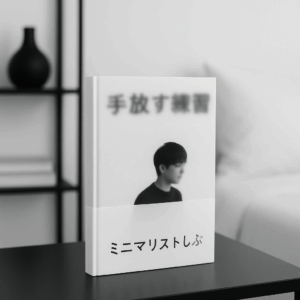
「捨てる」は終わりではなく、始まりだった
ミニマリストしぶさんの本を読み終えたとき、胸の奥に静かな衝撃が残った。
捨てることは“減らす行為”ではなく、“選び抜く意思”なのだと気づく。
物理的な整理が、精神的な自由へとつながる。そんな実感を、ページをめくるたびに覚えた。
手放すことの難しさと快適さ
何かを手放すとき、人は少なからず罪悪感を抱く。
まだ使えるかもしれない、思い出がある、いつか必要になるかもしれない——
その“かもしれない”に支配され、私たちは多くのモノと一緒に心のスペースまで占領されていく。
しぶさんは、
「捨てることは、未来の自分への信頼だ」と。
そのニュアンスが印象的だった。
モノを減らすことで、選ぶ力と感性が研ぎ澄まされ、
自分にとって本当に必要なものだけが残る。
それはまるで、心に風が通るような軽やかさだった。
“モードなミニマリズム”という生き方
彼のモノトーンな世界観に惹かれた。
黒と白、時にグレー。無駄を削ぎ落としたスタイルは、
ファッションであり、生き方そのものだった。
私はその女性バージョンになりたいと思った。
シンプルで、けれど芯がある。
物の少なさよりも、選択の一貫性に美を見出す女性。
彼のワードローブや部屋の配色から、“思考の整頓”を学んだ気がする。
選ぶことの美学 40代からの“減らす力”
40代になると、増やすよりも「残すもの」を決める力が問われる。
若い頃に憧れたブランドや流行も、今は自分の色に合わなければ無理に取り入れない。
それは妥協ではなく、成熟だ。
持ち物が少ないほど、日常は豊かになる。
そのシンプルさが、知的で凛とした印象を生む。
モードカジュアルを軸に、自分の“定番”を見つけていくこと。
それは単なるファッションではなく、思考と感性を磨く行為だ。
捨てることは、余白をつくり、
余白はまた新しい美しさを迎える空間になる。
暮らしに風を通す、2冊の本
心に残ったアイテム:
どちらの本も、“減らす”を目的ではなく“選ぶ”ためのツールとして語っている。
読み進めるうちに、心のどこかに溜まっていた曇りが少しずつ晴れていく感覚を覚える。
選んで、残して、生きる
ミニマリズムとは、持たない生き方ではなく、
自分に正直に生きるためのリセットボタン。
捨てることを恐れず、選ぶことを楽しむ。
その先に、きっと“自分らしさ”というモードが見えてくる。
※冒頭の画像はイメージであり、しぶさんではございません。
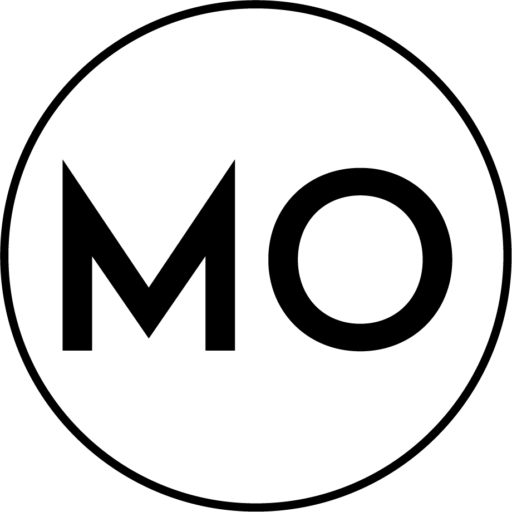
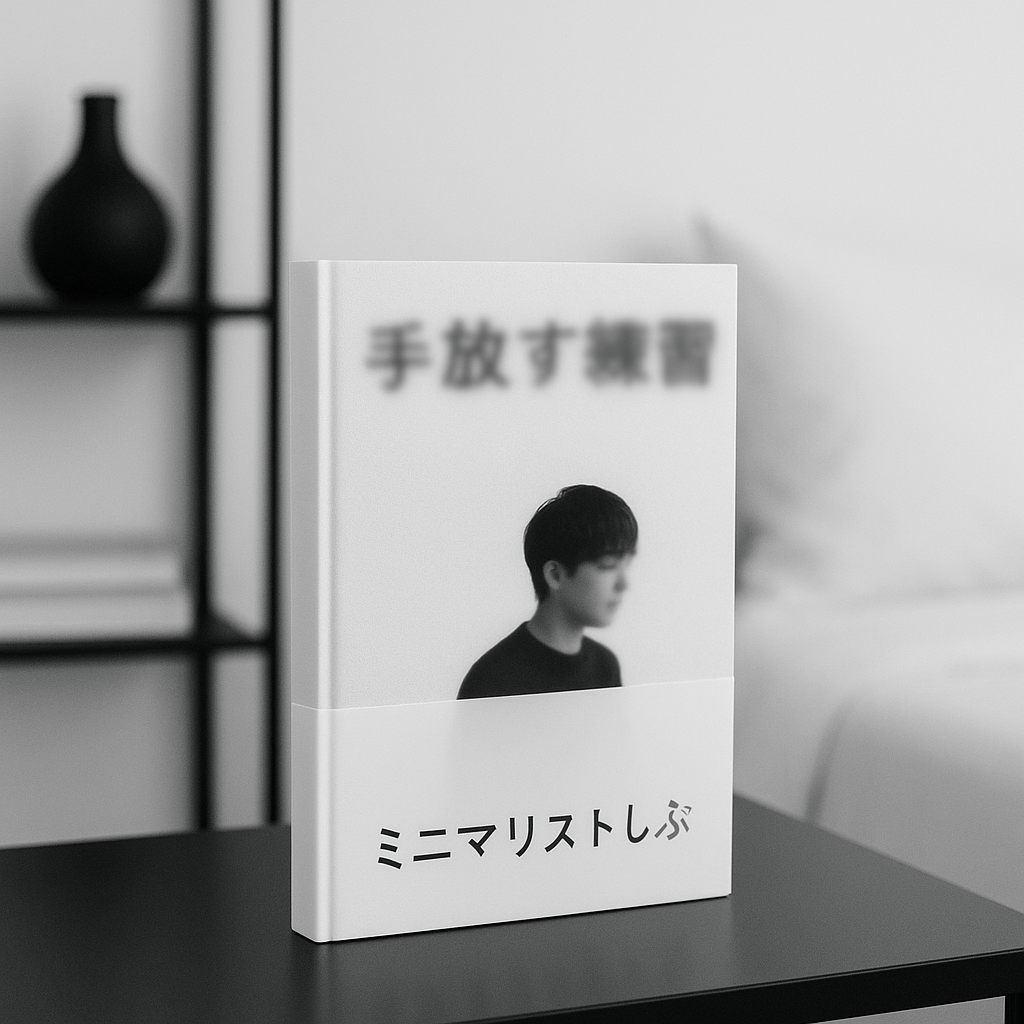
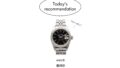

Comment